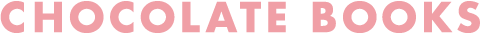同人誌版 「女神の娘は、復讐を果たしたい」 のエーリク視点SSです。
イソラと繋ぎを取ったあたりまでの裏話。
読了後のおまけにどうぞ。
愛しい人
喜びの日――。そのなんとも宗教的で大仰な名称のついた儀式に立ち会ったのは、父だった。
三年の孵化期間の後、ようやく姿を見せた女神はあまりにも幼く、父は苦々しい思いを押し隠すことに苦心したらしい。
「先代の女神より、10は若いだろう。一体、どうなっているのか……」
「今回も、女神の叡智は期待できないということですか?」
放浪先から呼び戻された理由を薄々察しながら、あえて知らぬ振りで尋ねてみる。
「おそらく。……私より、お前の方が分かるだろう? このままでは、ミレルは自滅する」
ミレル人であることを隠し各国を渡り歩いてきた俺への問いかけに、静かに頷く。
父は憂慮に満ちた表情を浮べ、薄く息を吐いた。
「第一神殿へ潜り込むことが出来れば、女神召喚に何が起こっているのか、エーランドが何を考えているのか分かるかもしれんが、ガードが固すぎてどうにもならない。そこで、だ」
「私に女神の従者になれ、というのですね」
先回りして口に出す。
父は安堵したように目元を和らげた。
「察しがよくて助かる。今の神殿はどうも一枚岩ではないらしい。女神召喚の秘密を探り、エーランドを追い落とす為の材料を持ち帰ってこい、エーリク」
優しい口調ではあったが、俺の答えは待っていない。それがよく分かる言い方だった。
放浪の旅に出る前、俺は家督相続権を放棄した。変人過ぎる兄・フランシスにこれ以上関わりたくない一心からの決断だったが、予想していた反対はなく、その代わり『一度だけ家長の命令を聞く』という条件を出された。
家長が父である間だけ、というので、俺はその条件を呑むことにした。その命令が、これなのだろう。
女神の従者というのは、ぶっちゃければ次代女神を孕ませる為の種馬のこと。
身体を売る対価として情報を手に入れる。クソみたいな仕事だが、これが終われば俺は完全に自由になれる。
諦めと希望の入り交じった複雑な気持ちで、第一神殿へとあがった。
エーランド・ヘンネベリとの目通りは、すんなり終わった。
もっと警戒されると思っていたのに、エーランドは俺を他の従者と同じように扱った。
若い頃はさぞ人目を惹いただろうと思わせる端整な顔立ちは、歳を重ねてもなお凛とした覇気を纏っている。
「従者の皆様方には、女神様の心身を癒す大切なお役目を担って頂きます。ですが、女神様の御意向が第一です。無理強いや乱暴は、この私が許しません。よろしいですね?」
エーランドが退出した後、残った高位司祭から閨でのあれこれが書かれた指南書を渡される。
……なるほど。さっきのは建前で、こっちが神殿側の本音ということか。
次代の女神は、女神の胎からしか生まれないらしい。
今代の女神は降臨したばかりだというのに、もう従者の用意がされている。彼女には、叡智を授ける公務を期待していないということなのだろう。
「なんだか、可哀想ですね」
俺と同じ結論に至ったのか、モンテンセン家の息子がポツリと言う。
カールステッド家の長男は首を振り、やんわり彼を窘めた。
「女神様を早く天の国へお返したいという御心あってのことかもしれないよ」
美しく咲き乱れた花。肌に触れる空気は、常に柔らかく暖かい。
大量の魔法力を使って維持された永遠の春が、ここにはあった。
それらは全て、女神の為。
神殿の頂点に立つは、女神。人知を超えた存在である女神が、今のミレルを歪めているのだとしたら――?
拳を握った俺の想像を、実際の女神はやすやすと超えてきた。
ミヤビ、という名の女神は、まるで子供だった。
この世界のことはおろか、自分のいる神殿のことさえ知らない。家への帰り道を忘れてしまった迷子のような娘だった。
無邪気で明るく、どこか危うい彼女は、与えられた従者と友人になりたい、と言い出した。
「夜伽とか、そういうのはいらないの。皆には話し相手になって欲しい」
そう言った口で、「次代の女神様は、賢いといいなぁ」などという。
誰一人閨へ呼ぼうとしないのに、一体どうやって子を孕むつもりなのか。
女神の性格を一言で表すのなら、『情緒不安定』に尽きた。
彼女は朝言われたことを、夕方にはもう忘れている。
何が引き金になるのか、時折、「帰りたい」と泣き始めることもあった。
その都度、従者は追い払われ、医療担当の高位司祭が女神を別室へと連れて行く。
しばらくして出て来た彼女は、泣いたことすら、いや治療を受けたことすら忘れていた。
女神に権力などなかった。彼女は、哀れなほど何の力も持っていなかった。
それでも、懸命に『女神としての役割』を果たそうと努力している。
俺以外の従者は、そんな彼女を我が子のように慈しみ始めていた。
俺が彼女に抱くようになった想いは、そんな綺麗なものではない。
「姫様」
俺は、彼女をそう呼ぶ。女神様でも、ミヤビ様でもなく、ただ姫様、と。
彼女から情報だけ引き出せればいい。家へ戻った後は彼女がどうなろうと構わない。初めは確かにそう思っていたはずなのに、俺の行動理由はいつの間にかすり替わってしまっている。
彼女を解放したい。彼女が泣かずに済む世界へと連れ出したい。
俺にとっての女神はもう、ただの「女」だった。
ある日、彼女の家庭教師である司祭に、呼び出された。
エーランドの養子であり、次代の大司祭候補に名前があがっている男だ。
警戒を高めつつ、指定された場所へと赴く。男――イソラが指定したのは、街外れの大衆酒場だった。
まっ昼間から、酒場?
不審に思いながら、了承の返事を送る。
イソラと会うことをロランに告げ、姫の護りはモンテンセンに委ねた。
「エーリク? どうしたの?」
無邪気に煌めく黒い瞳に後ろ髪を引かれる思いで、俺は神殿を抜け出した。
そして抜け出した先で、俺は衝撃的な事実を知らされた。
「――私がこの情報をあなた方に不利なように使うとは思わなかったのですか?」
去り際、イソラに問いかけてみる。
彼への心証は、正直悪かった。
家庭教師という名目で姫と二人きりで過ごしていることも気に入らなければ、彼女が懸命に書いている一の姫宛ての手紙の返事をもぎ取ってこないところも気に入らない。エーランドの懐刀という立場を差し引いても、俺はこいつが嫌いだ。
姫様に慕われてること自体が気に入らないのだから、どうしようもない。
「思いません。ミヤビ様の為にならないことを、あなたが進んでするとは思えない」
司祭服を脱ぎ、町民の恰好に着替えたイソラが口角をあげて答える。
俺達が店に入ってきてからずっと、こちらばかりみている女店員がほう、と熱い吐息を洩らした。
そのご自慢のツラで一の姫様にも取りいったのか。
……一の姫はまだ13かそこらだった筈。胸の中で舌打ちをして、店を出る。
先代の女神が、娘達の現況を知ったらどう思うだろう。
長女は、復讐に燃え高位司祭と手を組んだ。次女はといえば、男を宛てがわれ薬を盛られ、司祭達の都合のいいようにコントロールされている。生前の先代は非常に愛情深く、一の姫を溺愛していたという。
愛する娘達を非道な連中に奪われ、非業な最期を遂げた彼女に深い同情を覚える。
と、同時に固く決意した。
姫を同じ目には遭わせない。彼女だけはどんな手を使っても、護り切ってみせる。
神殿を厳重に守る神兵に見つかった時の言い訳用に、ちょっと良い酒を手に入れてから帰路につく。
自室に入るところを、姫に目撃された。
「あ~、ずるいっ!」
姫は頬を膨らまし、俺の手の酒瓶を指差す。
「エーリクだけ、いいなぁ。私も出かけてみたい! 次は誘ってよね?」
細い腰に手を当て、ぷりぷり怒っている。
ああ。また忘れたのか。
絶望で目の前が暗くなる。
女神は第一神殿を出てはならない。そう何度も大司祭に言われているというのに、姫はすぐに忘れてしまう。
俺のいない間に、また何かあったのかもしれない。
急がなければ。他の従者もこちら側に引き入れ、事あるごとに行われる司祭達の洗脳を何としても阻止しなければ。
無言で部屋に入り、扉にもたれかかる。
神殿が隠していた秘密は、思っていた以上に血なまぐさく残酷なものだった。
父が欲しがっていた情報は、もう手に入った。
従者を辞め、家へ帰り、得た情報でエーランドを追い落とす為の根回しを始める。
きっとそれが、ランツ家の次男として取るべき行動だ。
正解は見えているのに、それを選ぶことが出来ない。彼女をここに置いていくことは、どうしても出来ない。
神殿を出るのなら、彼女と共に。
たとえ姫と心中する結果になったとしても、俺がこの選択を後悔することはないだろう。
「エーリク。今晩は眠れそうにないの。部屋で本を読んで貰えない?」
夕食の後、歓談室で姫はそう言った。
得意気に片眉をあげ、俺にニヤリ、と微笑みかけてくる。
俺が酒欲しさに街へ降りたと勘違いしている彼女なりの意趣返しだ。
……ほんと馬鹿だな。
姫様も俺も、大馬鹿だ。
今までどんな相手にも覚えたことのない狂おしいまでの愛しさが、胸を食い荒らす。
「仰せとあらば喜んで」
俺はにっこり笑って答えた。