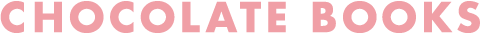ロイヤルキス様より配信中の「孤高の魔法使いは初恋の新妻を手放せない」の番外編SS。
本編には入れられなかったヒーロー父の事情と、エンディング後の一幕を父視点で。
本編読了後でないと意味不明なお話です。
エイリアスはその日、数年ぶりに離宮を出た。
王家の紋章が入った馬車に揺られて向かった先は、王都の外れにぽつんと立つ大きな望楼だ。
昔は見張りの為に使われていたというが、強固な魔法防壁が都の周りに巡らされて以来お役御免となり、今ではすっかり寂れている。
「ここまでいい。誰もついてくるな」
エイリアスは供をしてきた近衛騎士らを望楼の下に留めると、彼らに背を向け歩き始めた。
六角形の塔をくるむように廻らされた螺旋状の階段を、エイリアスは一歩ずつ踏みしめるように登っていく。
枯れ木を思わせるその細い背中を、騎士達は白けた表情で見送った。
彼らの心の中に、エイリアスに対する敬意はない。
現国王パトリックに命じられたから形ばかりの護衛をしているに過ぎず、前王の身を真に案じている者はここには、――いや、王国中を探しても一人もいなかった。
平和と繁栄を保っていたレヴェルト王国を混乱の渦に突き落とした愚王。
それがエイリアスだ。
エイリアスがあのまま離宮に引き籠り続けていれば、国は荒れ果て大勢の死者が出たことだろう。
あと一歩のところで世代交代が間に合った為、エイリアスはこうして五体満足で生きている。
もしも間に合わなかったのなら、耐えかねた民衆の手によって処刑されていたに違いない。
己を惜しむ人間が誰もいないことは、エイリアスもよく知っていた。
最後のあがきが徒労に終わった以上、寿命が費えるその日まで息をひそめて生きていくしかない。
そうだ、そうして生きていくしかない――自身に言い聞かせる度、エイリアスは真っ暗な箱の中に一人閉じ込められている気分になる。
エイリアスが生きる理由は、とうの昔に奪われていた。
生への執着は欠片もないというのに自ら命を断てないのは、最愛の人・ベアトリスとの約束があるからだ。
――『あなたは生きて、幸せになって。ジークのことは、その次に気にかけてくれたら嬉しい。お願いだから私のあとを追ったりしないと、今ここで約束して』
いつ儚くなってもおかしくない瀕死の状態にあってなお、ベアトリスの表情は出会った頃の輝きを失っていなかった。
エイリアスに向けられた愛情に満ちた眼差しに、他者への憎しみや怨嗟は欠片も見られない。
王太子に見初められたばかりに、半ば強引に王宮へ連れて来られた彼女は、後から娶った他の妃たちから言葉に出来ないほどの惨い仕打ちを受け続けた。
それでも、いつだってベアトリスの瞳は明るかった。
妃はベアトリス一人でいい。
エイリアスは何度も重臣たちに訴えた。
だが若くして王となったエイリアスに我を貫き通すだけの力はなく、身分の低いベアトリスを傍に置く代償として、四大貴族からそれぞれ一人ずつ妃を娶る羽目になった。
自分こそが王妃にふさわしいと言わんばかりの傲岸な態度で乗り込んできた彼女らに良い感情など持てるはずもなく、閨を共にする時はいつも部屋を暗くして最小限の触れ合いにとどめた。
ベアトリスを想いながら己を奮い立たせ、吐き気を堪えて義務を果たす。
口づけはおろか無垢な身体を碌に慣らされることもなく、顔が見えないよううつ伏せにされた状態での性急な交わり。
高貴な身分を誇る妃たちは皆、シーツをきつく握り締め、痛みと屈辱に耐えねばならなかった。
――これがお前たちの望みなのだろう?
苦痛に喘ぐ妃の背後にいる父親を嘲笑いながら、鬱憤を吐き出すように己の種をまいていく。
そうして子が宿ったあとは、二度とその妃の閨には行かなかった。
早く、早く、と気が急く。
全員を孕ませてしまえば、もうベアトリス以外の女に触れる必要はない。
どうせ世継ぎは周囲が決める。
ベアトリスにその気がないのなら、王太子になるのは誰だっていい。
よその女が生んだ我が子を、見に行くこともしなかった。
わざわざ見たいと思わなかったからだ。
あってしかるべき罪悪感は、心のどこを探しても見つからない。
その頃にはもう、エイリアスはどうしようもなく損なわれていたのだろう。
ベアトリスは常に明るく優しかったが、元々聖人君子だったわけではない。
理不尽なことには怒り、体調が悪ければ機嫌が悪くなり、気が乗らない時には豪快に怠ける。
出会った頃のベアトリスは、自由で率直な女だった。
そんな彼女が王宮では我儘を押し殺し、健気に振舞っている。
他の妃についてはいかなる言も、ついぞ発することはなかった。
初めての子が流れた時さえ、ベアトリスは取り乱さなかった。
申し訳ない、と深く頭を下げ、静かに涙を流しただけだ。
彼女の頬を濡らす涙を、エイリアスは我が子を失った悼みの発露だと受け止め、残念だが仕方ないと慰めた。
ベアトリスの身に何が起こったのか知ったのは、彼女がこの世から去った後のことだ。
頑なに口を噤んだのは、ベアトリスなりの意地だったのかもしれない。
たとえ修羅へ続く道だとしても、それは彼女が自分で選んだのだと、そう言いたかったのかもしれない。
だがそれだけではなく、哀れな夫が自責の念に駆られないよう、怒りに任せて他の妃を手にかけてしまわないよう、懸命に明るい面だけを見せていたのだろう。
直接ベアトリスを苦しめたのは妃たちでも、不幸の原因を作ったのはエイリアスだ。
自らを生き地獄へと突き落とした張本人の幸せを、ベアトリスは最期まで願っていた。
――『お願い、約束して。私のことは、忘れていいから』
臨終の際にあってもなお変わらない彼女の在り様に、エイリアスは身を捩って悶えた。
激しい悲しみと絶望、そして彼女を苦しめた者への憎悪が炎となって、身体の内側からエイリアスを焼いていく。
嫌だ、できない!! 頼む、私を置いていかないでくれ……!!
咽び泣きながら首を激しく振るエイリアスの手を、ベアトリスは青白く細い手で握りしめ、これだけは譲れないとばかりに同じ台詞を繰り返した。
握られた手は、酷く痛かった。
苦しい息の中、必死に言い募る彼女にエイリアスはとうとう頷くしかなくなる。
こくり、と縦に振られた首の動きを見届けた直後、ベアトリスは深々と息を吐いて目を閉じた。
安らかな死に顔だったと皆が言う。
だがエイリアスに葬儀の記憶はない。
最愛の妻との約束だから、自死は選べなかった。ただ、それだけだ。
――『ジークのことは、その次に気にかけてくれたら嬉しい』
本当はもっと強い言葉で託したかっただろうに、そうはしなかった彼女の思いを結局エイリアスは叶えられなかった。
ジークハルトにだけは、申し訳ないことをしたと思っている。
こんな筈ではなかった。
産まれるまでは、ベアトリスと二人で、今度こそ大切に、誰より慈しんで育てようと決意していたのだ。
それが、蓋を開けてみればどうだ。
ジークハルトに亡き妻の面影を見つける度、胸をかきむしりたくなるほど苦しくなった。
何故お前の方が生き残ったのかと、いつか本人を直接詰ってしまいそうだった。
せめてもう一つの約束だけは守ろうと惰性で呼吸する日々の中、自暴自棄と呼べる状態は通り越し、紙より薄く擦り切れた心は善悪の区別さえつけられなくなった。
狭く急な階段を、何とか最後まで登りきる。
望楼のてっぺんは東屋に似た造りになっていた。
手すりを両手で握り締め、目的の場所をじっと見据える。
王宮の麓にある大通りでは、盛大なパレードが繰り広げられていた。
裸眼では見えるはずもない遠くの景色がありありと見えるのは、使役精霊の魔法のお陰だ。
「あ、ほら見て、あそこ」
エイリアスの隣にふわりと浮かんだ風の精霊が歌う様に囁き、半透明の指でとある一点を指差す。
元はジークハルトが召喚したそれは、ウィニーと名乗った。
『――彼にどんな事情があったにしろ、私はあの魔法を許容することができない。どんなにそうしたくても、できないの。だからといって主を失えば、あとは静かに還るのを待つだけ。それも味気ないでしょう?』
ジークハルトに掛けられた禁呪が解け、自分を取り戻したエイリアスの前に現れた精霊は、開口一番そう言った。
唖然としたエイリアスだが、口を開く前に自身の異変を感じる。
青年時代に召喚して以来、ずっと傍にいた使役精霊の気配が消えているのだ。
『あの子なら今は隠れてる。私の力が強すぎるのね。あなたが風の気とも相性がよくて助かったわ』
エイリアスの心の中が読めるのか、ウィニーはこちらが疑問を発する前にスラスラ答えた。
「私は、お前と契約したのか……?」
「いいえ、それは無理。あなたに私を使うだけの魔法力はないもの。でも、私を存在させるだけの生命力ならある。そう長く生きたいわけではないのでしょう? 私が傍にいることで、あなたの寿命は縮むかもしれないけど、構わないわよね?」
何ともよく喋る精霊だ。
身勝手な要望を知らぬ間に押し付けられたことには呆れたが、寿命を減らしてくれるというのなら願ってもない話で、拒否する理由はない。
それに、精霊とはもともとそういった存在だ。
彼らは彼らの理で生きており、人間の事情に忖度しない。
今回の外出だってそうだ。
ウィニーがそうしろと煩かった為、エイリアスは渋々静かな離宮を出て、非難と軽蔑が浮かぶ騎士達の前に立ったのだ。
のろのろと、ウィニーが指差した方に目を向ける。
王族や大貴族が並ぶ特別席に、彼らはいた。
最初、柔和に微笑むその男が誰なのか、エイリアスは分からなかった。
目を凝らして見つめているうちに、ジークハルトだと気づく。
最後に会った時より伸びた髪を一つに結わえている。
右耳だけに下がっているサファイアブルーの宝石を嵌めた雫型のピアスに目を留め、それからもう一度顔全体を眺めた。
ジークだと分からなかったのは、その顔に浮かんだ表情のせいだ。
いつも無表情で陰気で暗い瞳をしていた男は、そこにはいなかった。
隣に座った婦人に、愛おしくて仕方ないと言わんばかりの眼差しを向けている。
明るく煌めく紫の瞳、陽光を受けて煌めく銀の髪。
――エイリアス!
かつて最愛の人が自分に向けてくれた何の曇りもない笑みが、ジークの顔と重なる。
エイリアスは息を止め、食い入るように我が子を見つめた。
ジークハルトの隣にいる女性は、身籠っているようだ。
ゆったりしたエンパイアドレスの腹部は、こんもり盛り上がっている。
彼女は己の腹を守るように、そっとその上に手を添えていた。
二人は先ほどから、ずっと笑い合っていた。
目前を通り過ぎていく華やかなパレードには時折視線を向けるものの、すぐにまたお互いの顔に戻る。
傍からみても、彼らが大層幸せなことは分かった。
ジークハルトは、最愛の人を見つけ、その手をしっかり掴んだのだ。
気づけば、滂沱の涙が頬を伝っていた。
見せたかった。ベアトリスに、今の彼の顔を。二人の姿を。
彼女は自分のことのように喜んだだろう。
ああ、よかった。
エイリアスは彼に何一つ良いことをしてやれなかったが、彼はしっかり日の当たる道を歩き始めているのだ。
「……一度は捨てた子でも、幸せを喜ぶ気持ちくらいは残っているものなのね」
ウィニーが平坦な声で、ぽつりとこぼす。
そうだ、その通りだ。
ベアトリスが亡くなった時、エイリアスは自分の子を全員捨てた。
最愛の妻が産んだジークも、例外ではなかった。
だが今、こうして彼が幸せそうに笑っているところを見ることができて良かったと、心から思う。
「人間って、本当に不思議ね」
ウィニーは独り言ちると、「もう気は済んだから、帰りましょう」と姿を消した。
途端、エイリアスの目前から、それまで拡大されて映されていた景色が消える。
遠い街並みをしばらく眺めたあと、エイリアスも踵を返した。
少し歩くだけで息が上がり、心臓が痛む。
もうそろそろ、逝けるだろうか。
ベアトリスと同じ場所へ辿り着くことはできないだろう。彼女は最後まで善人だった。
エイリアスが落ちるのは、地獄以外にない。
死してなお、二度と会えないことは悲しいが、今は一日も早く解放されたかった。
思い残すことは、もはや何もない。
ふと目を上げれば、雲一つない青空が見えた。
先ほどまで見ていたからだろう、ジークハルトの隣にいた夫人の瞳が浮かぶ。
ああ、まさにこんな色をしていた。
エイリアスは小さく微笑み、再び足を動かす。
彼が笑みを浮かべたのは、ベアトリスが息を引き取ってから初めてのことだった。